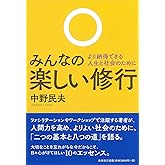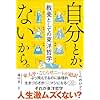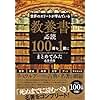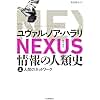エビデンス(科学的根拠)が重要とされる医療現場でさえ、ワークショップが、あるいはワークショップ的なチーム医療が重視されてきている。
エビデンスはもちろん大事で、治療法の選択肢を選ぶ目安として、長所短所を医師が説明したり、或いは薬剤データとして示される。
一方で、その患者さんの刻々の状態や思い、家族状態や実生活など、つまり「現場の状況」と「エビデンス」とされるものを多角的に総合して方針を選択する必要がある。
それはまちづくりや政策形成〜最近漸く言われだしたEBPM(evidence based policy making)などについても更に当てはまるだろうし、いろいろなアクターから提案が出て個々では思いつかなかったり出来なかったプランが生まれたりもするだろう。
自分たちで主体的に考えた事なら自発的に行動もできるし、アクター同士がつながることもできる。
根っこの方を考えると、今までの日本の教育で不足していたが求められているもの〜 自分の頭で考える、現実の状況や他者の思いを知る、更にそれらを踏まえて考える、そしてそれを伝える、プレゼンする〜
といった、今後益々先が見えなくなる世の中で個人も共同体も生き抜くための基礎としてとても役立つと思う。
会議と称して上司が一方的に方針を申し渡すような、あるいは「声の大きな人」が皆んなの時間を奪う長広舌で衆知を集められないような集まりでは、その組織は先細り、あるいはいきなり座礁しそうである。
例えば一回の発言を2分以内として全員が喋る、というようなことからだけでも必要だろう、、
芸術方面については、ワークショップで創造的なプラスの効果が期待できるのではないだろうか。
まずは小さく試みてみることが大切な気がする。
本書は多くの学びを与えてくれた。
| CARVIEW |
Select Language
HTTP/2 200
content-type: text/html;charset=UTF-8
server: Server
date: Mon, 06 Oct 2025 07:31:33 GMT
x-amz-rid: 0KPYGTRVVXB6QRMJKVWB
set-cookie: session-id=356-8876660-2646137; Domain=.amazon.co.jp; Expires=Tue, 06-Oct-2026 07:31:33 GMT; Path=/; Secure
set-cookie: session-id-time=2082787201l; Domain=.amazon.co.jp; Expires=Tue, 06-Oct-2026 07:31:33 GMT; Path=/; Secure
set-cookie: i18n-prefs=JPY; Domain=.amazon.co.jp; Expires=Tue, 06-Oct-2026 07:31:33 GMT; Path=/
set-cookie: lc-acbjp=ja_JP; Domain=.amazon.co.jp; Expires=Tue, 06-Oct-2026 07:31:33 GMT; Path=/
set-cookie: sp-cdn="L5Z9:IN"; Version=1; Domain=.amazon.co.jp; Max-Age=31536000; Expires=Tue, 06-Oct-2026 07:31:33 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly
accept-ch: ect,rtt,downlink,device-memory,sec-ch-device-memory,viewport-width,sec-ch-viewport-width,dpr,sec-ch-dpr,sec-ch-ua-platform,sec-ch-ua-platform-version
x-xss-protection: 1;
cache-control: no-cache, no-transform
content-encoding: gzip
content-security-policy: upgrade-insecure-requests;report-uri https://metrics.media-amazon.com/
accept-ch-lifetime: 86400
x-content-type-options: nosniff
content-security-policy-report-only: default-src 'self' blob: https: data: mediastream: 'unsafe-eval' 'unsafe-inline';report-uri https://metrics.media-amazon.com/
strict-transport-security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload
vary: Content-Type,Accept-Encoding,User-Agent
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-cache: Miss from cloudfront
via: 1.1 494a80066b7918f6a24c432c4f67a960.cloudfront.net (CloudFront)
x-amz-cf-pop: BOM78-P1
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
x-amz-cf-id: p_YF-Ozhdl1cgh9nsmxgIB1gWhKkXHsC8O_5w76aJk0GsMUSoLK6Fw==
ワ-クショップ: 新しい学びと創造の場 (岩波新書 新赤版 710) | 中野 民夫 |本 | 通販 | Amazon





無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ワ-クショップ: 新しい学びと創造の場 (岩波新書 新赤版 710) 新書 – 2001/1/19
中野 民夫
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
学校教育,企業研修,環境教育,芸術活動,まちづくりなどさまざまな現場で,ワークショップという手法が注目されている.参加体験型,双方向性を特徴とするこの新しい学びと創造のスタイルにはどのような可能性があるのか? 数多くのワークショップの企画・運営に携わってきた著者が豊富な事例を紹介しながらその意義を語る.
- ISBN-104004307104
- ISBN-13978-4004307105
- 出版社岩波書店
- 発売日2001/1/19
- 言語日本語
- 本の長さ236ページ
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻る
商品の説明
商品説明
住民参加のまちづくりの手法として、また、環境教育や社内研修のプログラムとして、「ワークショップ」が広がりをみせている。本書は、アメリカでワークショップを学び、その企画プロデューサーとして活動中の著者が、ワークショップの定義や意義、実際の事例、さらにはワークショップ手法を会議に効果的に取り入れていく方法などを分かりやすく説いた1冊だ。
ひと口にワークショップといっても、アート系、まちづくり系、自然・環境系などさまざまな分野で行われている。それらを丁寧に解説するとともに、著者が体験したり、企画したワークショップの事例を紹介する。著者が最も影響を受けたのは、アメリカのジョアンナ・メイシーのワークショップだった。湾岸戦争をアメリカで迎え、困惑しながら「戦争を止めるために、私たちになにができるでしょうか?」とメイシーに問いかけたとき、「その質問こそが出発点です。孤立せず、集いあって、問いあうことが力です」と返した彼女の答えが、著者にとってのワークショップの原点だったという。メイシーの言葉にワークショップの本質をみる思いがする。
また、ワークショップという場は、小さいころ、心ゆくまで遊んだ「遊び場」や「広場」にあたるものかもしれないという著者のたとえには、思わずうなずかせるものがある。ワークショップを単にマニュアル的に解説するのではなく、その本質にも触れさせてくれる好著といえる。(清水英孝)
内容(「MARC」データベースより)
学校教育、企業研修、市民運動などの現場で注目されている参加体験型、双方向性を特徴とする新しい学びと創造の手法=ワークショップ。その企画・運営に携わってきた著者が、豊富な事例をもとにその意義を語る。
登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2001/1/19)
- 発売日 : 2001/1/19
- 言語 : 日本語
- 新書 : 236ページ
- ISBN-10 : 4004307104
- ISBN-13 : 978-4004307105
- Amazon 売れ筋ランキング: 本 - 59,278位 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中3.9つ
5つのうち3.9つ
39グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2019年4月27日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入
- 2014年2月25日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入「ワークショップ」と呼ばれる場についての紹介と現実と可能性がわかる本。
目次を見ると歴史、実際、意義、応用、という感じでツボを抑えた作り。
論文を引いて説明することもあれば、ネイティブ・アメリカンのエピソードなどが紹介されることもある。
非常に柔軟な視点から書かれているようで、読んでいて楽しさがある。
みどころの一つは、「宗教と何が違うのか」ということにも触れているところ。
恐らく、ワークショップは自己啓発系の催し物と比較されることが多いのだろう。
この点にも触れているあたり、書き慣れているなぁと、感心する。
学び、場、融合、みたいなキーワードに関心があるなら一読する価値があります。
- 2016年7月23日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入自分が講座をする上で、どういう効果があるか、どうすると学びやすい環境になるかなど、講座をより良いものにするのに役立つかと思い、読んでみました。少し自分の必要としているワークショップと系統が異なる話も多かったけれども、根本的な面で参考になりました。自分がする講座は学習・教育系のワークショップに当たったのですが、この系統は「先生のお話を聞くことが中心になりがち」という傾向があり、参加者に主体的に関わってもらうにはどうすればよいが、またそうするために、共に学ぶというスタンスをもつこと、妄信的に聞いてもらうのではなく、突然賢くなるのではないので地道に取り組む必要があることをお互いに理解した上で、参加者の様子やニーズを見ながら進めていく、という点が確認できてよかった。少し古い本ながら、きちんとワークショップの分類などを丁寧に説明してあるので、ワークショップの何たるかを知るには非常に便利な本。
- 2021年1月5日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入筆者が、どのような人生を送ってきたか、そして世界をどのような目で見ているのかがよくわかる。
自分の人生観をちょっと変えてくれそうな一冊!
- 2010年9月19日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書環境問題や自然破壊の問題を考えるとき、「知識伝達や啓蒙的な活動だけでは、必ずしも人々を実践に誘うのには役立たない。p.44」
「まず「知るよりも感じること」が関心を呼び起こし、「理解」そして「行動」へと進んでいく前提となることが、この分野の指導者たちに実感としてはっきりしてきた。
そして、ここ十数年の間に自然の中での体験をまず重視した参加体験型のプログラムや体験学習の手法がうみだされ、「キャンプ」「セミナー」「ワークショップ」など様々な催しで実践されてきている。p.44」
「参加者が受け身でなく、積極的に関わる研究集会P.12」であるワークショップは、アート系、まちづくり系、社会変革系、自然・環境系、教育・学習系、精神世界系、統合系p.19-20といった多岐にわたっている。
「現代の様々な困難は、まさにこの「唯一の解答」のない問い、正解を持った教師などいない問いであり、これらに対して、私たちが取り組んでいく方法としてワークショップの可能性をp.39」みることができる。
「ワークショップとは「その中で安心して成長したりうまれ変わったりできるゆりかご」だという説明の仕方も有る。P.143」
人と人とのつながりと共感を広げていくことにより、社会の問題を解決し、個々人の可能性を広げていくことができるワークショップの魅力がおおいに語られている。ワークショップの実践方法というよりは、その可能性について、説得力のあるとても魅力的な語り口で説いている本。
- 2009年6月21日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入ファシリテーターとしてワークショップに参加時、ぶち当たった壁を壊してくれる一冊でした
会議やミーティングでは、方向感のないだらだらとした会議にうんざりする事も多い
皆、会議をしている素振りで、心を留め置くことが無いまま無用な時間がただただ過ぎる
ただお話を聞いてほしいのか、ディベートしたいのか、内容が無さ過ぎる
総て、司会進行やテーマの選別、タイムスパンなど、準備なし+思いつきで臨む会議に多い失敗だ
イエスマンばかりが集まり、顔色を伺いながらの「会議ゴッコ」の域を脱さない
この一冊は、ワークショップの目的となる効果的な会議運営、問題解決への導き方、取り組みについて様々な方向で読めるので面白い。
その他:妊婦さん向けの教室運営にも役立つ
妊婦向けの母親学級運営は、ここ数年で、既存の机上講習から参加型体験学習へとシフトチェンジしてきた
一昔前は、出産施設における独自の価値観刷り込みや不要な情報、時間の垂れ流しが殆どで
読めば分かる内容に無駄な時間を割いて読み聞かせ、殆どが顔見せや自己紹介で効果が低く
参加者も生むのだからしょうがないと渋々参加、後にあんなものなのかと評価が低かった
女性に力を引き出す方法を授けなかったり、信頼関係という身勝手な思い込みとエゴの元に
任せておけば安心、何とかしてくれるはずだろうと期待だけ膨らませて放置しておいてと、
対象を低いところに置きすぎていたのである。エンターテイメントとしての教室に過ぎなかった。
□海外におけるワークショップは非常にバリエーションに富、内容が充実しているのになぜ日本では・・・
(菓子やお茶を出し、お友達作りが母親学級?たまひよや育児雑誌の内容を話し聞かせることが本当に子どもを産み、育てていく女性を支える力に繋がると考えているのなら本末転倒)
なぜ、日本でできないのか? 次世代に考える力や機会を与えないのか?
主体となる女性に、どのように産み育てて生きたいかをディスカッションさせないのか?
出産経験が違うと方法や内容が浅く狭くなるのは避けられないのか?と不思議でした
(マザークラスは日本の2〜4回の倍に当たる8〜10回で、資料は一切持たず、デモスト・体験中心で、夫婦参加も多い。
時間帯も夕方や子連れ参加あり、話し合いながら進めるという画期的なワークショップを見て、
驚きと同時に、これまでのTOPダウンした取り組みを振り返り恥ずかしさを感じた)
ワークショップは時間と内容と媒体に方向感を持たせながら、経験を引き出し、効果を出すに最も良い
見て知る、知って知る、感じて知る、触って知る、体得してみると5要素総てを満たし、個人に落としやすいのだ
ファシリテーターは総ての発言機会を得て、それらに方向感を持たせる重要なキーマンとなる
そこから生まれだされたオリジナリティー溢れるアイデアは、双方にとって得るものが多い
双方向性ある学級運営を推奨し展開し、広げることは合併症予防やリスク管理に有益となる
人材の無駄、時間の無駄、資源の無駄、自己満足でしかない会議から、卒業しましょう
- 2013年5月14日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書ワークショップの喜びに満ちている本である。
2001年に書かれている本なので、10年以上も前である。
まだまだ、ワークショップがここまで社会に広まっていなかった時期ともいえる。
ワークショップに参加したことがある人なら、その進め方や手法、効果などは実感済みであろうし、できることとできないことも何となくつかめていることだろう。
本書では、基本的な部分の説明や今となってはほとんどの人が知っていることの説明が多くなっているが、それだけこの10年の変遷と普及は大きかったということだろう。
しかし、だからこそ、導入された初期の頃のシンプルな形でワークショップの本質的な意義やはたらきをつかむことができる。
ワークショップの本質は、10年たっても変わらず、むしろ今読み返しても響いてくる。
輪になって座って、対話する。
シンプルな中に力があります。
“途方に暮れていた私は、あまりに直接的な質問だとは思いながらも、「戦争を止めるためには、私たちになにができるでしょうか?」という問いをぶつけた。
すると彼女は、即座に「その質問こそが出発点です。孤立せず、集いあって、問いあうことが力です。問うことほど強力なことはありません。自分自身に、友人たちに、繰り返し繰り返し問うことです」と返してきた。”
- 2014年1月28日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入ワークショップ第一人者が書かれた内容は、解りやすく参考になるところが多くありました。

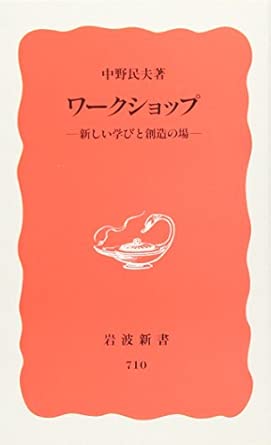


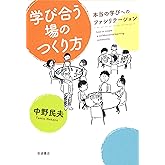
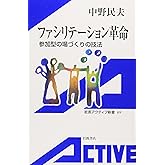
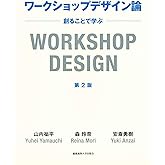
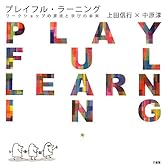
![ワークショップ・デザイン[新版] 知をつむぐ対話の場づくり](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/716Z8NEGDpL._AC_UL165_SR165,165_.jpg)