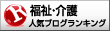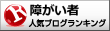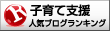私は3人の子どもを育ててきました。
一番上の子は知的障がいがあり、支援が欠かせない生活でした。
その後に生まれた2人目と3人目は、いわゆる「普通の子」です。
ただ、2番目の子は幼い頃、よく嘘をつく子でした。
「宿題は終わった?」と尋ねると「もう終わったよ」と笑顔で答えるのですが、
実際はやっていなかった――そんなことがたびたびありました。
私は責めたい気持ちを抑えながらも、
「信頼できる人になってほしい」という願いから、
嘘をつかれた人の心情を丁寧に伝えるようにしました。…
嘘をつかれたときの葛藤と対応
私はよく「宿題は終わった?」と尋ねていました。
すると息子はにこっと笑って「もう終わったよ」と答えるのです。
私は安心して晩ご飯の支度に取りかかるのですが、
数日後に先生から「宿題が溜まっています」と伝えられる。
実は故意にやっていなかったのです。
嘘をつかれたと知ったとき、親としては裏切られたような気持ちになり、
つい責めたくなるものです。
ですが私は、叱るよりも「嘘をつかれたとき、相手はどう感じるのか」を
伝えることが大事だと考えました。
「お母さんは大切に思っているあなたに嘘をつかれて、
とても悲しくて悔しい気持ちです。
あなたの言葉を信じていいのかわからなくなります」
そんなふうに、私が感じたことを素直に伝えるようにしました。
繰り返すうちに、嘘は少しずつ減っていきました。
親は子どもを無条件に信じる存在であるべき
たとえ嘘をつかれても、親が子どもを無条件に信頼する姿勢は必要だと思います。
なぜなら、子どもは「親から信頼されている」という実感を、
自分への自信に変えていくからです。
その自信こそが、さまざまな物事に挑戦し、成長していく力の源になるのです。
一方で、子どもは親のことを無条件に信じるわけではありません。
成長するにつれ、親を客観的に見られるようになります。
だからこそ、親が子どもにどう接するかは一層大事になっていきます。
知的障がいのある子と「普通の子」の信頼関係の違い
上の子は知的障がいがあり、身の回りのことができるようになるまでに
時間がかかりました。
長く支援が必要だったため、信頼は時に「依存」に近づきやすく、
自立を促す関わりはとても難しかったのです。
一方で下の子は、学校や友人との関わりの中で、
親以外の大人を比較対象にしながら「人の見方」を学んでいきました。
次第に「親も一人の大人」として評価するようになり、
親の誠実さや態度そのものが、信頼を得るか失うかの分かれ道になっていきました。
子どもから信頼される親の行動とは
信頼される親とは、誠実さを持ち、
子どもを「家族として大切にすること」と「ひとりの人間として尊重すること」
の両方を実践できる人です。
普段から子どもとの関係性を丁寧に積み重ね、
危機に直面したときには最優先に寄り添う。
そして、子ども自身が考え、判断することを尊重する。
どちらか一方でも欠ければ、信頼は少しずつ削られてしまいます。
成人した子どもが親をどう見るか
子どもが成人すると、親を「ひとりの大人」として客観的に評価するようになります。
そのとき、もし親が価値観を押し付けたり、
家族への配慮を怠っていたりすれば、「信頼できない人」と
判断されてしまうこともあります。
医療や福祉の現場でも、大人になった子どもが親を見放してしまう場面に
出会うことがあります。
そこに残るのは「血のつながり」だけ。
信頼のない親子関係はとても脆いものだと痛感します。
信頼は親自身の幸せにつながる
親子関係の信頼が大切なのは、子どものためだけではありません。
親自身の人生の幸せにも直結するからです。
高齢になっても仲の良い親子は、子どもが心から親に感謝しており、
連絡を取り合ったり旅行に出かけたりして思い出を重ねています。
その姿は本当にあたたかく、親子の絆が人生を豊かにしていると感じます。
私は、障がいのある子と共に歩んだ経験、
そして他の子の成長を見守った経験から、
「親は子どもから信頼を得にいく存在であるべき」だと強く思うのです。
おわりに
子どもに嘘をつかれて悩んだ日々も、
今となっては親子で信頼を学ぶ大切なきっかけでした。
信頼は一方的に得られるものではなく、
日々の誠実な積み重ねによって築かれるものです。
「親だから当然信頼される」と思わず、
ひとりの大人として子どもから評価される存在になる。
その努力を続けることで、子どもが成人した後も支え合える関係が残り、
親自身の心を満たしてくれるのだと思います。
親は子どものためだけでなく、自分の幸せのためにも、信頼をとりにいくのです。