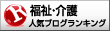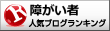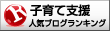ステージが変わるとき、人は試される
人生にはいくつものステージがあります。
学生から社会人へ、独身から結婚へ、親になり、
そしてまた子どもが巣立っていく。
あるいは、病気や介護、転職、引っ越しなどによっても、
人は新しいステージに立たされます。
そのたびに、私たちは「これまでの自分」で歩み続けるのか、
それとも「新しい自分」に育ち直すのかを問われます。
私は障害児の母として、また障害福祉の現場で30年以上活動してきた中で、
幾度もその岐路に立たされてきました。
例えば、娘が生まれたとき。重度の障がいがあることを告げられ、
世界が一変しました。
これまで当たり前と思っていた子育てのイメージは通用せず、
療育・医療・福祉の知識を一から学ぶ必要がありました。
まさに「人生のステージが変わった瞬間」だったのです。
そのとき感じたのは、「学び続けなければならない」という切実さでした。
知らなければ子どもを守れない。
支援につながらなければ孤立してしまう。
必死に本を読み、専門家に聞き、仲間と情報を交換しました。
振り返れば、その積み重ねが、今の私を形づくっています。
年上から「生き様」を学ぶ
新しいステージを歩むとき、必ず助けになってくれたのは
「先にその道を歩いた人たち」でした。
私が地域で障害児者のコミュニティに加わったとき、
すでに成人した子どもを育てた先輩お母さん方がいました。
彼女たちは、ただ制度や情報を教えてくれるだけではありませんでした。
病気の告知を受けたときの絶望感、療育に奔走した日々
、思春期の葛藤、そして「親なきあと」をどう考えるか——
そのすべてを、自分の言葉で語ってくれました。
そこから私は「生き様」を学びました。
支援制度の穴に泣きながらも諦めない姿勢、周囲からの無理解に
心を痛めながらも子どもの存在を誇る強さ。
本には書かれていない“人生そのものの学び”が、そこにはありました。
年上を敬い、その経験を素直に受け取ること。
それは、私自身が次の世代に何かを渡していくうえでも、大きな礎になっています。
年下から「時代」を学ぶ
一方で、私は年下の世代からも多くを学んできました。
例えば、SNSやデジタルツールの使い方。
私が子育てに必死だった時代には想像もしなかった方法で、
若い世代の保護者や支援者たちは情報を集め、つながりを作り出しています。
LINEグループで即座に情報共有したり、
Instagramで当事者や家族の声を発信したり。
最初は「そんなことできない」と思っていました。
でも、彼らから教えてもらい、一歩踏み出すことで、
自分の世界は大きく広がりました。
年下だからといって軽んじていたら、私は時代から取り残されていたでしょう。
「上を敬い、下を見くびるな」。
この言葉は、福祉の現場でこそ深く実感します。
年上の人の経験に耳を傾けることも、
年下から新しい時代の風を受け取ることも、どちらも等しく必要なのです。
学び続けることが「子どもたちの未来」につながる
障害児者福祉の世界は、常に変化しています。
制度が変わり、用語が変わり、支援の形も変わっていく。
数年前に通用した常識が、今では古いものになっていることも珍しくありません。
だからこそ、親も支援者も学び続けなければならない。
それは「自分のため」だけでなく、「子どもたちの未来のため」なのです。
私が36年間子育てをしてきて実感するのは、
学び続ける姿を子どもは必ず見ているということです。
母が諦めずに学び続けている。その背中を子どもたちはちゃんと受け取っています。
変化は誰にとっても怖い
人間は本能的に変化を嫌います。
脳は「現状維持」を安全と捉えるからです。
だからこそ、新しい学びを始めるときには抵抗感が強く出ます。
私も何度も「もう年だから」「若い人に任せたほうがいい」と
言い訳をしそうになりました。
でも、小さな一歩でいい。
「新しい用語をひとつ覚える」
「スマホでできることを一つ試す」。
その積み重ねで脳は「これで大丈夫」と書き換わり、
やがて変化が当たり前になります。
まとめ——ステージが変わるたび、人は育ち直せる
人生のステージが変わるとき、人は必ず試されます。
そのとき大切なのは、「学び続ける力」。
年上からは生き様を学び、年下からは時代を学ぶ。
どちらも受け取りながら、変化の波に自分を合わせていく。
障害児者福祉の世界で私が歩んできた経験は、それを教えてくれました。
子どもを支えるために学び続けることは、自分自身の人生を豊かにし、
そして次の世代に希望を渡していくことにもつながります。
「上を敬い、下を見くびるな」。
その姿勢で、これからも私は学び続けたいと思います。
あなたは今、どんな学びを通して「次のステージ」に備えますか?