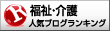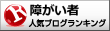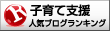「子どもに学んでほしいことを、あなた自身が行いなさい」
これはインド独立の父、マハトマ・ガンジー(愛称:バプジ)の教えです。
バプジは、子どもは教科書よりも大人の言動から学ぶことの方が多いと
考えていました。
だから、「言うことは聞け。でも真似はするな」
という教育方針には強く反対していたのです。
子どもに学んでほしいなら、まず大人が自らそれを実践すること。
バプジは親や教師にそう語りかけ、人々を導いてきました。
この言葉を読んで、私は「まさにその通りだ」と頷かずにはいられません。
なぜなら、私自身が親との関係で苦しみながらも、
親を反面教師として生きてきたからです。
私の親は“毒親”だった?
私は子どもの頃から、母にとっては
「できて当たり前」「できなければダメな子」という扱いを受けてきました。
褒められた記憶よりも、否定された記憶の方がずっと強く残っています。
母は世間体を大事にする人でした。
障害のある子を持った私を「恥ずかしい」「人に言えない」と
口にすることもありました。
私は「母の期待に応えなければならない」という呪縛の中で育ち、
自分らしさを押し殺すような毎日でした。
大人になって「毒親」という言葉を知り、ああ、私はまさにその中で育ったんだな…
と気づいたとき、胸の奥にずっと重しのように沈んでいたものの正体が
わかった気がしました。
反面教師としての選択
だからこそ、私は母とは真逆のことをしようと決めました。
母のように「支配する」子育てではなく、私は「寄り添う」子育てを。
母のように「人と比べる」のではなく、私は「その子自身を見つめる」子育てを。
もちろん、母からは滅茶苦茶言われました。
「甘やかしすぎ」「そんなやり方じゃこの子はダメになる」…。
でも私は、母に従うよりも、子どもにとって本当に必要なことを選びたかったのです。
私の子どもは知的障害があり、口唇口蓋裂という先天的な課題も抱えていました。
周囲からの視線や言葉はとても厳しく、時に心が折れそうになりました。
それでも、私が心に決めていたのは
「子どもにとって安心できる存在であり続ける」ということでした。
母のように「恥ずかしい」と言わず、「大丈夫だよ」と伝え続ける。
母のように「世間の目」を気にせず、
「あなたが生きていてくれるだけで素晴らしい」と伝える。
これが、私なりにバプジの教えを実践した姿だったのだと思います。
子どもは親の言葉ではなく行動を学ぶ
バプジの例でよく語られるのが、スマホや食生活の話です。
親は子どもに「ゲームばかりしないで」と言いながら、
自分はずっとスマホをいじっている。
子どもに「野菜を食べなさい」と言いながら、
自分はお菓子や菓子パンばかり食べている。
そんな姿を見た子どもが学ぶのは、「言葉」ではなく「行動」です。
「スマホは大事なものなんだ」「甘いものを食べるのが普通なんだ」…
そのメッセージは確実に伝わってしまいます。
私も子育ての中で何度も気づかされました。
「子どもに怒らないでほしい」と思うなら、
まず私が冷静に対応しなければならない。
「自分を大切にしてほしい」と願うなら、
まず私が自分を大切にする姿を見せなければならない。
子どもは親の背中を見て育つ。
その言葉の意味を、私は日々体感してきました。
親である自分が“学び続ける人”でありたい
私の母は、私に「こうあるべき」という押しつけばかりを与えました。
けれど私は、自分の子どもに「あなたのままでいい」というメッセージを
行動で伝えたい。
だから私は今も学び続けています。
障害福祉の現場で人と関わりながら、自分自身も成長し続けること。
母から受けた痛みを、次の世代に引き継がないように、自分で止めること。
親が変われば、子どもも変わります。
そして、子どもが変われば、その子の未来も変わっていく。
最後に
バプジの教えを借りれば、子育てとは「自分自身を律すること」と
同じなのだと思います。
子どもに学んでほしいことを、まず親である自分が実践する。
私にとって母は反面教師でした。
けれど、そのおかげで私は「どう生きたいか」を
深く考える機会を与えられました。
今、私は胸を張って言えます。
「私は、子どもに安心と希望を渡せる親でありたい」
そう思って歩んできたことこそが、私の生き方の証しです。