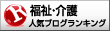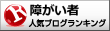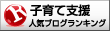先日、ダイヤモンド・オンラインの記事で
「現場を改善しないリーダーのワースト1の特徴」が紹介されていました。
その内容を読んで、思わず「これだ!」と納得したのです。
私自身、障害福祉の現場に長く身を置き、現場改善に取り組んできました。
努力もしているし、学び続けてもいます。
でも、なぜか周りのリーダーが「変わらなさすぎる」と感じることが多く、
どうすればよいのか悩み続けているのです。
改善しないリーダーの最大の特徴:「仕組みで解決しようとしない」
記事によれば、現場を改善しないリーダーの最大の特徴は
「仕組みで解決する」という発想がないことだそうです。
「根性でなんとかしよう」「気合いで乗り越えよう」――
そんな言葉をよく耳にします。
でも、それは再現性がなく、同じ問題が何度も繰り返されてしまう。
私も現場で、似たようなトラブルが何度も起こり、
そのたびに同じ説明を繰り返す…そんなことが日常茶飯事でした。
私は「仕組み化」「ルール化」をしていかないといけないと考え、
学びを続けているのですが、どうしても周りが「人」に頼るやり方から
抜けられないのです。
表面的な対処で終わる現場
「とりあえず今日はこれでしのごう」「来週になれば落ち着くから」
――そんな発想で動いていると、根本的な問題は解決されません。
私が関わる現場でも、同じような光景を何度も見てきました。
そのたびに職員は疲弊し、利用者さんにもしわ寄せがいきます。
一方で、私が学んできたのは「トラブルは仕組みの不備」として捉える視点です。
ルールがなければ作る。属人的な運用になっていれば誰でもできるように整える。
これを徹底すれば、同じ問題はほとんど起きなくなるのです。
頭ではわかっていても、組織全体がその視点を持てなければ改善は進みません。
そこが私の一番の悩みです。
「人」に頼りすぎるリーダーの危うさ
改善しないリーダーは
「◯◯さんなら頑張ってくれる」「△△くんに任せておけば安心」と考えがちです。
けれど、これは一見合理的に見えて、実はリーダーの責任放棄です。
本来、リーダーがすべきことは
「誰がやっても同じ成果が出るように仕組みを整えること」。
特定の人材に頼らず、標準化されたプロセスを用意することです。
私は「誰がやってもできる仕組み」を目指して何度も提案してきました。
ですが「今までこのやり方でやってきたから」「人を増やせば解決する」
という返事ばかりで、なかなか前に進まないのです。
リーダーには「仮面」が必要
感情に任せて人を責めても、現場は良くなりません。
冷静に構造を見極め、仕組みに手を入れることが大切だと記事には書かれていました。
私もリーダーとして、時には「仮面」をかぶる必要があるのだと思います。
感情を抑えて、冷静に「これは個人の問題ではなく、仕組みの問題だ」と伝え続ける。
けれど、そう割り切って動いても、現場全体の意識が変わらなければ改善は進まない。
そのギャップに、正直言えば悩まされ続けています。
それでも学びをやめない理由
「自分は努力しているのに、なぜ周りは変わらないのか」
――そう感じることは少なくありません。
ですが、そこで立ち止まってしまえば、結局何も変わらないのだと思います。
私が学び続けているのは、「いつか現場が本当に変わる瞬間が来る」
と信じているからです。
仕組みを整えれば、同じ問題に振り回されることはなくなる。
その確信があるからこそ、試行錯誤を続けています。
おわりに
「現場を改善しないリーダーの特徴」を読んで、
改めて自分が悩んできた理由がはっきりしました。
仕組みで解決する発想がないまま、人に頼り、
表面的な対応だけを繰り返している――それでは現場が疲弊するのは当然です。
私は、これからも仕組みづくりを学び、実践し続けたいと思います。
そして、いつか「誰がやっても同じ成果が出る」現場を実現し、
障害のある方も支援する職員も安心できる場をつくりたいのです。
変わらない現場に悩みながらも、私が学び続ける理由は、
そこに希望を見ているから・・・そこに尽きるのです。