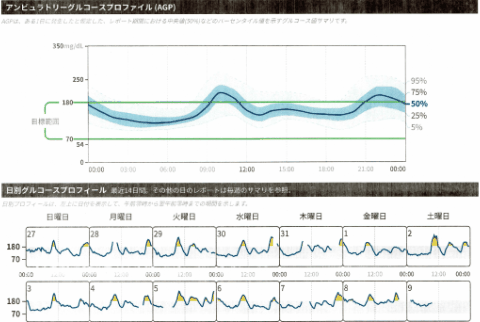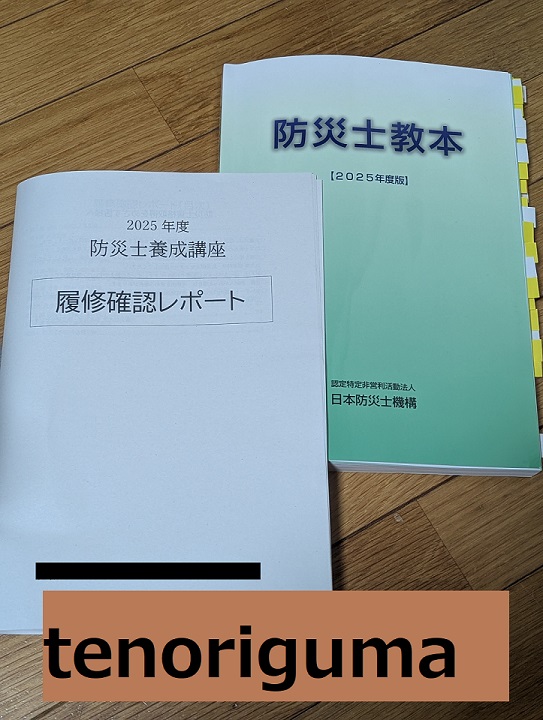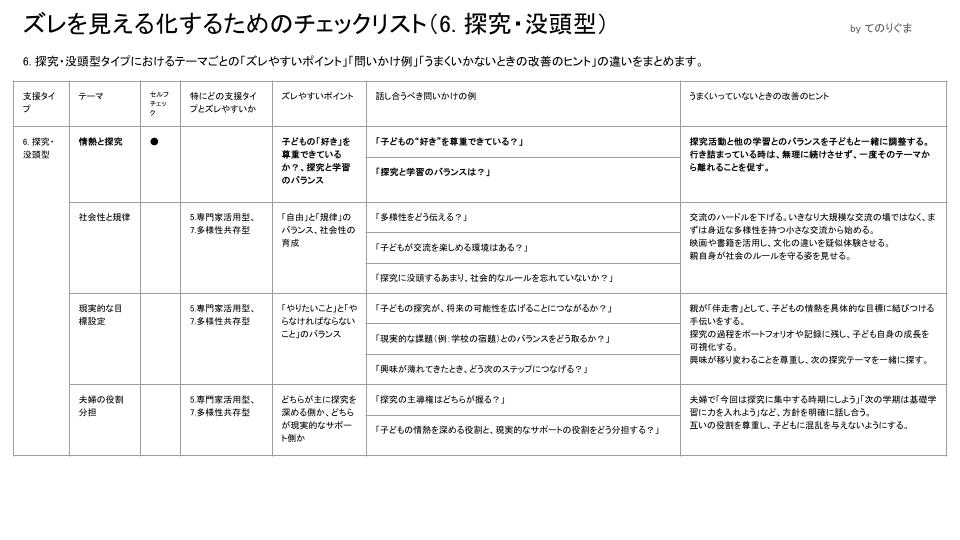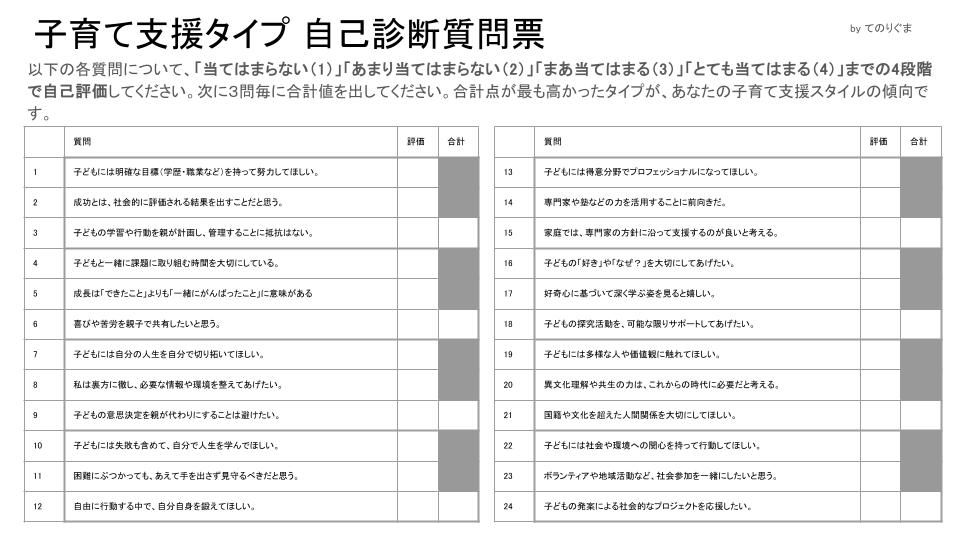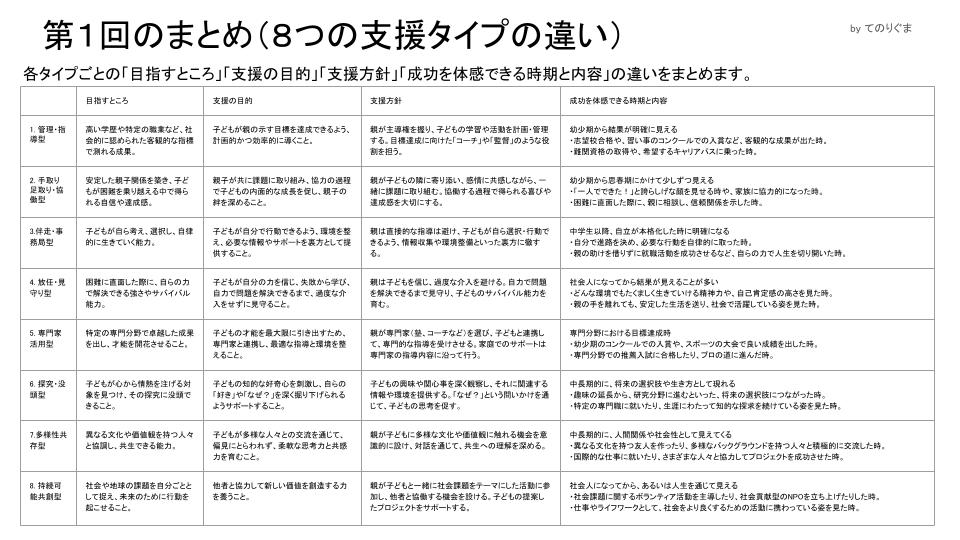<はじめに>
親族が詐欺に引っかかり、てのりぐまは通信関係の緊急対応を担当しました。
エンジニアとしての長年の知見を活かし、ネットワークと端末の両面から多層的な防御を構築しました。この記録は、被害拡大の防止と親族の安全確保という2つの観点から実施した具体的なステップです。(いずれの対応も警察と相談済みです。)
大前提として、親族の心のケアは全メンバーで最優先で実施しています。
だれでも引っかかり得るという認識のもと精神的なサポートを欠かしませんでした。
<ステップ1:緊急遮断>
アクション:固定電話の電話機、スマホ全部、パソコンを親族から一時的に預かる。
目的:詐欺犯との接触機会を物理的にゼロにするため。
詳細:
親族宅の機材(物理)をすべてもれなく回収。
<ステップ2:安全な連絡手段の確保>
アクション:代替端末の調達と設定。
目的:親族に対する安全確保のため。
詳細:
・てのりぐまが携帯電話を契約して親族に貸与
・端末はガラホを調達する
・ガラホでできることは、電話を受けるのと電話をかけるのみとし、あとの機能は契約や設定で使えなくする方針
・設定は、てのりぐまがロックし、暗証番号は私しかしらない状態にする
・調達の流れ
1.キャリアと端末に関する事前調査。
2.ショップにガラホの在庫の確認をし、すぐにショップに行く旨電話予約。
3.ショップで端末の購入と、通話専用とする契約を実施。
4.初期設定作業に関する素案をショップに提供、共同作業として実施。
<ステップ3:最強の防御設定ー再度の接触を許さない盾>
アクション:代替端末を最強の盾とするためのセキュリティ設定。
目的:詐欺犯からの再度の接触を許さない。
詳細:
・契約レベル
契約上で、通話のみ可能とした(ガラケープランを選択しネット機能を遮断する旨申し入れ)
(★ブラウジングとキャリアメールはあきらめる)
・ネットワーク設定レベル
ネットワークの初期設定で、国際通信の完全抑止(海外への発信と海外からの着信を行わない)を実施
・端末レベル(着信拒否)
端末の初期設定で、電話帳登録外着信拒否設定を実施(電話帳登録外着信拒否機能を持つ端末を調達)
・端末レベル(SMS拒否)
端末の初期設定で、危険SMSの拒否や非通知SMSの拒否設定を実施
・未実施事項
初期設定時にショップの担当者と協議したが以下が未実施
ネットワークの初期設定で、迷惑電話ブロックの機能が可能かトライしたが、機能提供が終了していたため未実施
端末初期設定における、自動通話録音と警告アナウンスの設定は未実施
<まとめ>
今回の対応が、同様の被害に遭われた方の助けになれば幸いです。
被害に遭われた方を責めず、安全と心のケアを最優先にすることが再被害を防ぐ上で何よりも大切と思います。