しあわせを招く七福神の物語 

七福神(しちふくじん)とは、その名のとおり「福」や「徳」を授けてくれる七柱の神様のことです。七福神は、人々に笑顔としあわせを届ける神々として、古くから日本中で親しまれています。
この七柱の神様たちは、実は出身もさまざまです。日本・中国・インドの神々が一堂に会した、国境を越えた、いわば「幸福の合同チーム」なのです。まずは、日本の神様である恵比寿(えびす)から紹介することにしましょう。にっこり笑うお顔が印象的で、商売繁盛や交通安全、そして大漁祈願の神として信仰されています。
次に、大きな袋を背負った大黒天(だいこくてん)はインドの神様ですが、慈しみ深く、大黒天は人々に「満な福」と「開運」をもたらす神様として知られています。
美しさと芸術の守り神といえば、唯一の女神である弁財天(べんざいてん)ですが、この弁財天もインドの神様ですが、音楽や学問、芸の道をきらめかせる存在として、多くの人に慕われています。勇ましい鎧姿の毘沙門天(びしゃもんてん)は、金運と勝運の象徴する神様でインドの神様です。毘沙門天は戦勝・勝負ごとに関係して、努力する人を力強く後押ししてくれる神様として知られています。
そして、にこやかなお腹で幸せを呼ぶ布袋(ほてい)は中国の神様です。大きな袋を持つ笑顔の福の神で、寛大さ・満・笑いの象徴とされています。布袋は中国の唐代に実在した僧であると言われています。
長いおひげの福禄寿(ふくろくじゅ)と、穏やかな笑みの寿老人(じゅろうじん)は、中国の神様で、どちらも健康長寿のご利益で知られています。福禄寿や寿老人は、その姿から仙人のようですが、昔、秦の始皇帝が不老長寿の秘薬を探し求めたことから、不老長寿という夢の象徴が「福禄寿」「寿老人」のような仙人像に具象化されていったそうです。
にっこり笑う七つの神様がそろうと、そこには必ず温かな幸せの風が吹くものです。江戸時代の中頃から、七福神は庶民の間で「福を運ぶめでたい神様」として人気が高まり、今では新年を祝う縁起物として欠かせない存在になりました。七福神は、今日も私たちの暮らしに小さな福を届けてくれるありがたい存在になりました。
 正月 イベントイラスト 七福神と梅と小判
正月 イベントイラスト 七福神と梅と小判
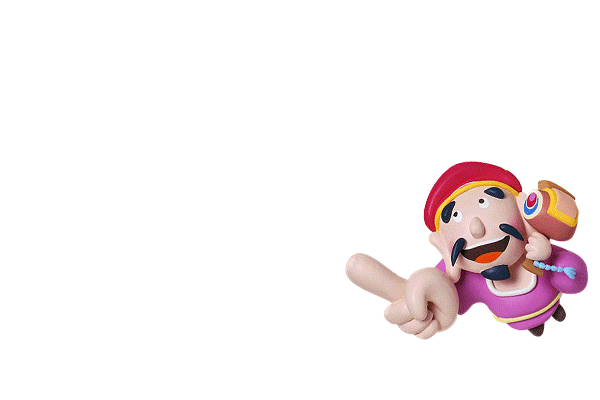
イラストの無断転載を禁じます。ご利用をご希望の方は(株)アートバンクまでお問い合わせください。












