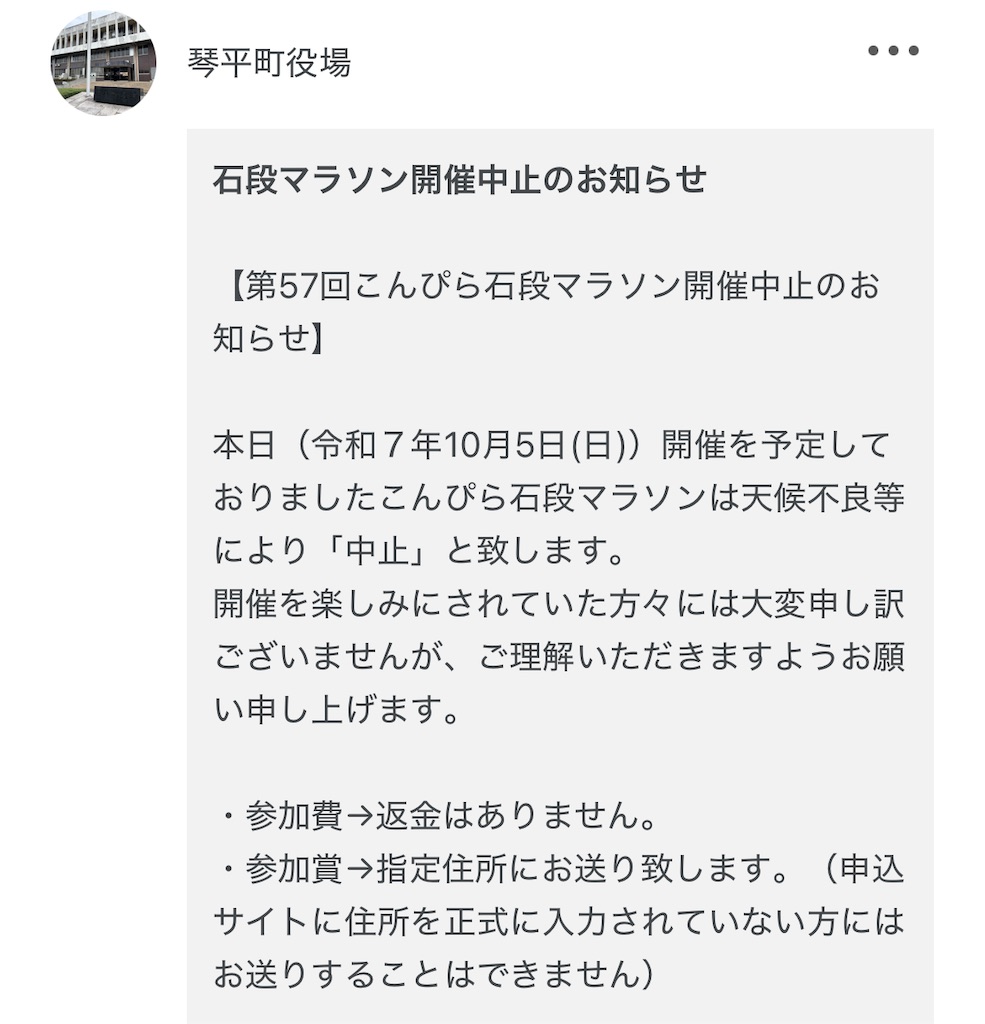1、作品の概要
『ろまん燈籠』は太宰治の短編小説集。
16編からなる。
新潮文庫より刊行された。
1941年~1944年の作品が集められた。
2、あらすじ
①ろまん燈籠
ロマンス好きの5人の兄妹。
彼らは、退屈するとよく合作で物語を作っていた。
あるお正月に末弟がラプンツェルを主人公に物語を書き始めるが・・・。
②みみずく通信
新潟の学校で講演をしたとある小説家。
彼と学生たちの微笑ましい交流。
③服装に就いて
かつて若いころに奇抜な服装を好んでいた私。
しかし、今では見る影もなく着る者にお金をかけなくなってしまっていたが・・・。
④令嬢アユ
鮎釣りに伊豆の温泉場に出かけた佐野君は、とある令嬢に一目ぼれし、作者に結婚の相談をする。
しかし、彼女は令嬢などではなく・・・。
⑤誰
ある作家は、学生たちとの交流において「なんじはサタン」と言われ、その言葉を酷く気にするようになる。
鬱々とした彼は、過去に借金申し込みの手紙を送った先輩のもとへ赴くが・・・。
⑥恥
和子は小説家の戸田に手紙を送ってその後に発表された彼の小説。
彼女は自身がモデルであると確信し、戸田に2通目の手紙を送るが・・・。
⑦新郎
明日のことを思い煩わずに一日を生きる。
戦争で家庭生活が貧するようになっても、彼の人のように日々を大切に、新郎のような心持で生きていくこと。
⑧十二月八日
昭和十六年十二月八日、日本が米軍に対して宣戦布告した日。
とある小説家の妻の、貧しくも平凡な一日。
⑨小さいアルバム
Dのもとへ遊びに来た客人に出す酒もなく、かといって外に飲みに出る金もない。
窮余の策で、開示した自身のアルバム。
⑩禁酒の心
なんとも酒は魔物。
戦時の配給で、思うように酒を飲むことができないご時世に、作者は禁酒を志す。
⑪鉄面皮
自分の書きかけの小説「右大臣実朝」を紹介、宣伝する作家。
開き直って平気で自作を引用する姿は、まさに鉄面皮。
⑫作家の手帖
七夕の短冊に、幼女が書いた願いはこの国の守護を神に祈る内容で、いつになく心に沁みた。
昭和12年7月7日に盧溝橋に響いた1発の銃声、戦争へと避けようもなく突入していく中、無心に歌い洗濯をする女たちに戦争の将来への楽観を感じる、
⑬佳日
成り行きから元学友の大隅君の結婚を世話することになった私。
立派な武士の家柄の小坂氏の娘さんを大隅君の嫁にもらうため、奔走する。
そして、北京から大隅君が帰国するが彼の尊大な態度に私は・・・。
⑭散華
ことし、私は三井君、三田君の2人の若い友人と死に別れた。
病弱だったため薔薇の大輪が散るように静かに逝った三井君、そして南方の島で玉砕して護国の神となった三田君。
詩人だった三田君。
彼の戦地からの手紙、「大いなる文学のために、死んでください」という言葉が著者の心を強く捉えていた。
⑮雪の夜の話
しゅん子は、身籠った義姉のために持って帰ろうとしたスルメを落としてしまうが、いつしか兄に聞いた、「景色を眼の中にたくわえる」ことを試みて、雪景色を見渡す。
そうして、雪景色を義姉に届けようとするが・・・。
⑯東京だより
誰も同じような風貌で工場で働いている少女たち。
しかし、その中の1人が特別に美しかったその理由とは・・・。
3、この作品に対する思い入れ、読んだキッカケ
本棚の片隅で眠っていた太宰治の短編小説集『ろまん燈籠』ですが、あまり読んだ記憶がなく、ひょっとすると20年以上積読していた1冊だったかもしれません(笑)
最近、なんだか日本近代文学ブームで、太宰の文章も読んでいてとても心地よく、独特のユウモアに笑い転げながら読んだりしていました。
こんなにリズミカルで、サービス精神旺盛な文章を書く人だったのかと、彼の文学の魅力の虜になりました。
4、感想(ネタバレあり)
短編小説集『ろまん燈籠』は、1941年~44年の3年間に書かれた短編小説を集めた新潮文庫編集の作品集で、太宰治の新潮文庫の本としては17冊目で最後のほうの刊行となったようです。
まあ、悪く言うと残りものみたいになってしまうでしょうか。
『ヴィヨンの妻』『パンドラの匣』『富嶽百景』『女生徒』みたいな有名な短編小説たちよりは少し地味な印象がある作品群となっています。
しかし、読んでみて小作品ならではの血肉の通った率直な感情といいますか、日常の中のささやかな感情の揺れ動きに触れるような作品が多く、こういった作品群もとても好きだと思いました。
1941年~44年というと、背景に太平洋戦争の暗い影が兆します。
逃れようもなく、米英との戦争へと突入していく日本。
そんな中、太宰治も作家である以上ににいち日本国民であり、国の動向に一喜一憂したり、勝利を信じて疑わなかったささやかな愛国者でもありました。
健康状態のために兵役につけなかった負い目もあったかと思いますが、どうにか戦地で頑張っている兵隊たちの力になりたい、戦争で困窮している日常の中に一筋の光を見出したい。
そんな純粋な願いが感じられました。
たくさんの情報が手元にあって、当時の状況が俯瞰できる今では愚かな妄信と彼の態度と文章は揶揄されるかもしれませんが、閉ざされた状況の中で日々の出来事に一喜一憂して、誠実に文学を紡いでいった太宰治という作家の在り方を、僕は肯定したいです。
ただ、国家や戦争を批判する文章を書けなかったので、これらの作品たちが100%彼の書きたかったことなのかはわかりませんが、私的な印象ではそう遠く本意から外れたような作品は書いていないように思えるのです。
戦中にこれほどに旺盛な創作をした作家はいなかったようですね。
滅びと死の香りに呼応して、水を得た魚のように生き生きと書いている。
あとがきにもありましたが、意地の悪い見方をするとそうも感じられます。
①ろまん燈籠
『愛と美について』の続編ともいうべき作品とのこと。
ラプンツェルを主人公に兄妹がそれぞれの持ち味ででリレー小説を紡ぎますが、これが非常に個性的で面白かったです。
しかし、めんどくさそうな兄妹ですね(笑)
②みみずく通信
太宰が新潟高校に講演に行って、生徒たちと交流するさまが描かれていますが、どこかユーモアと洒落があって読みやすいですね。
この講演のあとに佐渡ヶ島へ渡り、『佐渡』を執筆しました。
③服装に就いて
「ほんの一時ひそかに凝ったことがある。服装に凝ったのである」との書き出しで始まるが、「服装にほんの一時凝ったことがある」と書かずに、こういう回りくどい書き方をするのが太宰っぽい感じがします。
高等学校の時のおしゃれにまつわる狂態の模様は短編小説『おしゃれ童子』に描かれていましたが、太宰の十八番の滑稽譚が冴え渡る佳作だと思います。
それから時は流れて、吝嗇家になった太宰は、まともなセル1枚も持ち合わせていない。
かつてのおしゃれ童子はどこへやら。
それでも彼の作品の中には服装にまつわる描写が多く、服装に対しての関心は高いように思いますが・・・。
それだけ裕福な実家にいた時に比べて経済状態が悪いことと、酒と交際費に消えていっているということでしょうか?
④令嬢アユ
純真な友人の仄かな恋心。
令嬢アユの正体。
でも、とてもいいひとですね。
タイトルのつけ方が絶妙。
⑤誰
学生のたわごとでサタンと言われたのを鬱々と気にする、気弱で小心者の太宰。
自分の失敗や、小心者なところを大げさに書いて、ユーモアにしているところはあると思うのですが。
聖書を読んで、キリストを尊敬していた一面も感じられる作品。
しかし、先輩にあてた手紙と、それに対しての先輩の朱筆の評がほとんど事実だというからひどいですね(笑)
「後日談はない」という締めは秀逸。
⑥恥
作家が書いていることがすべて真実だと思ってはいけないということですね。
若いころに、「なんでこの作家は僕が感じていたことがわかるのだろうか?」みたいなことを思ったことが一度や二度ではありませんが、これも若さゆえ自意識の強さゆえのことでしょう。
書き出しの「菊子さん。恥をかいちゃったわよ。ひどい恥をかきました。」が唐突な感じで印象的ですね。
友人に向けての1人称の告白体という形もユニークで、小気味良いリズミカルな文体で読ませる短編だと思いました。
⑦新郎
太平洋戦争前夜。
水平線の向こうから暗雲が垂れ込めるごとく、徐々に日本に不穏な空気が満ち始めていたころ。
「明日のことを思い煩うな」とキリストの言葉を引用して太宰は言います。
ちょっと空元気というか、自分自身にも言い聞かせているというか、そんなふうにも捉えられますが、優しく真面目に生きようとしている太宰の姿はどこか健気でもあります。
新郎の心で生きているとは。
恐れ入った。
⑧十二月八日
太宰の奥様をモデルにした短編。
主婦の視点から、米英に対して開戦した日の東京の日常を描いています。
政府の情報統制もあり、開戦当初は楽観ムードが強かったのでしょう。
真珠湾攻撃での米艦隊に甚大な被害を与えた成果も大きく報道されていたようですね。
トラトラトラ。
素朴な心情で、日本国の勝利を願う書き方が良いです。
⑨小さいアルバム
他人が家に遊びに来て、酒もなにもなくてアルバムを見るとはずいぶんと侘しいものですが、そこで語られている半生もまた・・・。
「幸福そうな風景ですね。いつまで続く事か」という言葉はこれから起こる破滅を予兆していたかのようにも取れました。
⑩禁酒の心
太宰必殺の滑稽譚。
戦時下の配給酒にまつわる、人々の意地汚さ。
いっそ禁酒すればというが、できるものか。
「なんとも、酒は魔物である」とは、けだし名言でありますね。
激しく同意致します。
⑪鉄面皮
『右大臣実朝』はよほどの力作だったのか、この短編でしきりに引用しています。
発表前の作品を引用しまくるの大丈夫なのとか思いますが、書き下ろしならまあオッケーみたいですね。
こんな所業をすると批判されると思ってか、他人から揶揄される前に「鉄面皮」と自己防衛。
⑫作家の手帖
七夕の幼女の清き祈り、「この国をお守りくださいませ」という言葉に心を打たれる太宰。
しかし、昭和12年7月7日は盧溝橋事件が起こった日でもあり、7月7日というロマンティックであるはずの1日は血なまぐさい意味も帯びてしまった。
講演での企業戦士とのやり取り。
この時期の太宰は、何かと物事の良い面を光を汲み取ろうとしているようにみえます。
大戦争の中においても、近所の主婦の無邪気な様子を見て、日本の勝利を確信する太宰。
今のように情報が多くなかった時代でもあると思いますが、初心さを感じる甘い短編と評すると彼の人は怒るでしょうか?
⑬佳日
事実をほとんどそのまま書いた短編だそうですが、どこかじんとくる美しい小説でした。
瀬川教授は、井伏鱒二のことみたいですね。
太宰は彼に頭が上がらないでしょう。
小坂一家が武家の一家ということもあり、凛として気高くも情が深く、ぜひ息子の嫁にという感じでした(笑)
今の結婚とあまりに違い過ぎて笑えるを通り越して、あっけにとられたりします。
新郎が正装してなくて、ギリギリで服借りるとかありえんし!!
しかし、最後に涙を流しながら笑っている大隅君が良かった。
⑭散華
大いなる文学のために、死んで下さい。
自分も死にます、この戦争のために。
太宰の家に出入りして学生の三田君が送った手紙。
詩人だった彼の文章が、心を打ちます。
最初、この小説のタイトルは『玉砕』だったといいます。
1944年3月。
華々しく開戦したが、徐々にじり貧になっていった当時の状況が偲ばれます。
⑮雪の夜の話
とてもロマンティックでリリカルな話。
少女の視点から書かれているのも清くて良いですね。
夜の雪景色がとても幻想的です。
⑯東京だより
1人だけ美しく感じた工場の事務の少女が、生まれつき足が悪かったようで、それが故の美しさと個性を太宰はその事実を知る前に感じていました。
精神と肉体の聖痕。
24時間テレビの過剰な障害者への賛美みたいな感じになると違和感を感じてしまいますが、太宰は自身の鋭敏な感性でその美しさを感じていました。
5、終わりに
どれもとても地味な話なのですが、逃れようもなく戦争に突入していく日本で、鋭敏な感性で日常を捉え続けた太宰の短編小説は、珠玉の輝きを放っていました。
精神が安定している時期の太宰は、地方のお金持ちの家で生まれただけにどこかお人よしで、すぐに感激してしまうのですが、そんなセンシティブなところも共感できて良いです。
hiro0706chang.hatenablog.com
hiro0706chang.hatenablog.com
hiro0706chang.hatenablog.com
hiro0706chang.hatenablog.com
hiro0706chang.hatenablog.com
hiro0706chang.hatenablog.com
↓ブログランキング参加中!!良かったらクリックよろしくお願いします!!

にほんブログ村