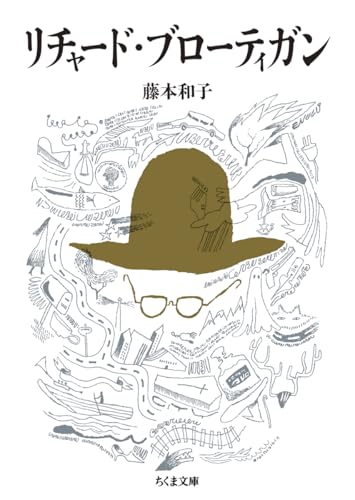スワンの刺繍が完成した。なんちゃってロングアンドショートステッチの野性味あふれる羽並。図案は蓬莱和歌子さん。

NHKテキスト『すてきにハンドメイド』2024年12月号に掲載された図案で、ダイソーのアルミフォトフレームに収めるために、縮小コピーしたもの。柔らかく、織目が荒い二重ガーゼに刺したからか、ステッチに囲まれた部分がすこし歪んでしまった。


接着芯を重ねると刺しやすいと聞き、やってみる。今のところ、違いはよく分からない。刺しにくいと言われるセリアのファブリックカレンダーにも、接着芯は使っていない。もしかすると、図案用の刺繍シートが刺すときの支えになっているのかも。刺繍シートは、図案写しと刺すときの補強材にもなる、というのは言いすぎだろうか。


チェキminiサイズにカットした梱包用の緩衝シートをくるみ、裏をマスキングテープでとめて完成。簡単だし、あとでブローチにしたくなったときにアレンジしやすそうだ。

初版から23年の時を経て、ちくま文庫に藤本和子の『リチャード・ブローティガン』がラインナップされる。私は新潮社版を持っているけれど、『るきさんの文庫手帳2026』とあわせて予約注文した。
このブログでもたびたび「私が好きな三大小説家」のひとりとしてリチャード・ブローティガンを挙げてきた。でも、本当のところ、リチャード・ブローティガンではなく藤本和子が好きなのかもしれないと思うほど、この本に打ちのめされ、支えられた。見ること、書くこと、その言葉に。
わたしだって、名もない、などとかんたんにいうが、そのようないいかたは、ほんとうはきらいだ。そう呼ばれる人びとには、いつだって名はちゃんとあるし、名もないといってすませるのは、語り手の思いあがりにすぎない。物語を書くことの目的の一つは、「名もない」と一括される人びとの名を固有名詞にして呼びもどし、かれらの声を回復することにあると、わたしは思う。わたし自身の書くものも、どうかそうであってほしい、と祈るように願う。
それには熱をおびた予感があるほうがいい。描こうとする対象に理由はわからないままに惹かれ、物語を書くうちに、自らのなかにあった名づけられない感情や思念にゆっくりと光があてられてゆくだろうという予感、あるいはそれまでは無知でいた視覚を発見するだろうという予感。