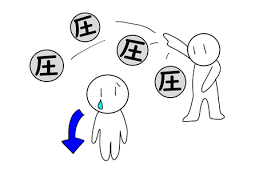就職活動や転職活動をしていると、「資格って意味あるの?」「結局、資格より実務経験じゃないの?」という声をよく耳にします。ネットでも「資格は無意味」「就活には役立たない」という意見がちらほら。
確かに、すべての資格が即戦力や内定につながるわけではありません。しかし、「資格は意味がない」と一刀両断するのは言い過ぎです。
資格が強みとして機能するかどうかは、その資格が次の3つのパターンのどれかに当てはまるかどうかにかかっています。そのあたりについて、今回はまとめていきたいと思います!
①業務に必須な資格
これは最も分かりやすいパターンです。
たとえば、学校の先生や調理師などは、資格がなければ業務ができないと法律で定められています。このような資格は「ある・ない」で応募のスタートラインが決まるため、就職や転職において圧倒的な価値を持ちます。
あとは日常的に車を運転する仕事ならば、運転免許も業務に必要になると言えますね。
こういった資格を持っていれば、履歴書に書いた時点で即戦力と判断されることも少なくありません。
②能力を示す資格
直接的に業務の必須要件ではないものの、自分の能力・素養を客観的に証明する手段として使える資格です。役割としては学歴に近いですね。
代表的なのは、TOEIC、ITパスポート、簿記検定などです。
たとえば、TOEICで高スコア(例えば800点以上)を持っていれば、英語を使う部署やグローバル展開している企業において評価されることがあります。
資格を通じて「この人は努力できる人だな」「基礎的な知識はあるな」と判断してもらえる可能性があるため、書類選考や面接でプラスになることは十分にあります。
③興味・熱意を示す資格
これは一見すると評価されにくいように思われがちですが、応募先の企業や職種との関連性が高い場合に強力なアピール材料になります。
例として、以下の3つを挙げてみます。
・お菓子メーカーに応募する際に「チョコレート検定」を持っている
・未経験から経理職を目指す際に、簿記3級を取得している
・アパレル業界を志望し、「ファッション販売能力検定」などを持っている
これらは業務に直接必要な資格でも、特別難しい資格でもないかもしれませんが、「その分野に強い関心がある」「自分から学ぼうとしている姿勢がある」ことを示す材料になります。
特に未経験職への転職では、「ポテンシャル」や「興味・学ぶ姿勢」が評価対象になるため、こうした資格が意味を持つケースは決して少なくありません。
まとめ:資格の価値は“文脈”で決まる
「資格は意味があるのか?」という問いに対して、答えは「資格による」かつ「文脈による」です。
次の3つのいずれかに該当する資格であれば、就職・転職活動において十分に武器になります。
・業務に必須な資格
・能力を示す資格
・興味・熱意を伝える資格
資格によっては複数当てはまることも多く、その場合は特に強力な武器になりますね。

ちなみに僕の実体験、というか自分語りとなるのですが、簿記2級を持っていることが評価され、新卒で大手企業の経理職になることが出来ました。簿記がなくても経理の仕事をすることは不可能ではないですが、以上の3つをある程度満たしていたと言えるのではないでしょうか?
もちろん面接や筆記試験が最低限出来ていることは前提です。強い資格を持っているのにSPI等の筆記試験が出来なかったり、面接がうまくいかなかったりすると、折角の努力も水の泡となるでしょう。僕も資格さえあればうまくいくだろうと思っていた時期がありました…。
さらに言えば、これらに当てはまらない資格(全く関連性のない趣味資格など)は、「意味がない」と言われてしまうのも仕方のないところ。
資格取得には時間もお金もかかります。せっかくなら、自分のキャリアプランと照らし合わせて、「意味のある資格」を選んでいきましょう。